やなぎだクン ―アルマイトの栞 vol.194
 なにやら気になり続けて二ヶ月くらい前から繰り返し読んでいる本が、角川ソフィア文庫版の柳田国男『山の人生
なにやら気になり続けて二ヶ月くらい前から繰り返し読んでいる本が、角川ソフィア文庫版の柳田国男『山の人生』で、とっくの以前に読んだとばかり思っていたのだけれど、自室の書棚を調べたら、それは柳田国男の『山民の生活』だったことが判明し、この表題の紛らわしさは『初めて使うAndroid設定ガイド』と『初心者のためのAndroid完全ガイド』の紛らわしさに似ている気がしてならず、まさか柳田国男は、読者が間違えて同じ本を二冊買ったりするのを目論んだのではあるまいな、とか疑念を抱きもするのであって、その点も含め、ちょっとイロイロ、本人を呼び出して問い詰めてみたい気分ではある。
間に挟んだ機材 ―アルマイトの栞 vol.193
 いまとなっては相当に旧式なシンセサイザーやらの諸々の旧い電子楽器を音源として、Macで録音やミキシングなどをするためには、音源とMacの間に「インターフェイス」と呼ばれる機器を挟む必要があるので、それを貸してもらい、シンセやらを音声ケーブルでインターフェイスに接続し、そこからUSBケーブルでMacへ接続して音を録ったら、元の音とは驚くほど違う音が録音されていてナニゴトかと思い、音色も音程も、まるで身に覚えの無い奇怪な音が再生される。例えて云うなら、「ピアノの音色でド・レ・ミ」と入力したら「チャルメラの音色でファ・ラ・レ」なわけで、このインターフェイスは音痴ではないのか。
いまとなっては相当に旧式なシンセサイザーやらの諸々の旧い電子楽器を音源として、Macで録音やミキシングなどをするためには、音源とMacの間に「インターフェイス」と呼ばれる機器を挟む必要があるので、それを貸してもらい、シンセやらを音声ケーブルでインターフェイスに接続し、そこからUSBケーブルでMacへ接続して音を録ったら、元の音とは驚くほど違う音が録音されていてナニゴトかと思い、音色も音程も、まるで身に覚えの無い奇怪な音が再生される。例えて云うなら、「ピアノの音色でド・レ・ミ」と入力したら「チャルメラの音色でファ・ラ・レ」なわけで、このインターフェイスは音痴ではないのか。
カオスなカバー ―アルマイトの栞 vol.192
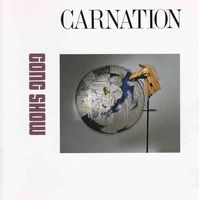 いつだったか、日が暮れてからエレキベース弾きの友人と会って安い呑み屋を探しながらウロウロしていると、都内では珍しい銭湯の煙突を目にし、「あ、『夜の煙突』だ」と二人揃って口走り、それはカーネーションのアルバム『GONG SHOW
いつだったか、日が暮れてからエレキベース弾きの友人と会って安い呑み屋を探しながらウロウロしていると、都内では珍しい銭湯の煙突を目にし、「あ、『夜の煙突』だ」と二人揃って口走り、それはカーネーションのアルバム『GONG SHOW
』に収録された名曲『夜の煙突』を揃って反射的に連想した結果なのだが、もし同じ状況で他の知人に向かって『夜の煙突』と口にしたなら、「あ、森高千里の」と返答される確率が高く、カーネーションのオリジナル曲より森高千里カバー曲のほうが有名になっていて、YouTubeで『夜の煙突』と検索すれば、カーネーションがカバーだとしか思えぬ悩ましい検索結果となる。
妖怪をあきらめて ―アルマイトの栞 vol.191
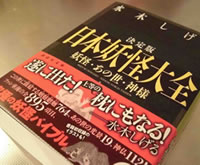 子どもたちのブームに便乗するわけではないけれど、講談社文庫に加わった水木しげるサンの『決定版 日本妖怪大全 妖怪・あの世・神様
子どもたちのブームに便乗するわけではないけれど、講談社文庫に加わった水木しげるサンの『決定版 日本妖怪大全 妖怪・あの世・神様
』は、本自体が「文庫本の妖怪」なのかと思う厚さ4cmのシロモノで、そこに巻き付いた帯には「遂に出た! 枕にもなる!」と、妖怪の甘言らしい文字が躍って人を化かす気らしく、しかし重要なのは「決定版」の文言である。決定してしまったのだ。日本の妖怪に関して事典を編むことは、もう誰にも許されない。なんか、日本中の子どもに「あきらめ」を教えてるみたいで気が引けるのだが。少なくとも、「将来の夢は妖怪の仲間に加わることです」と卒業文集に書いても、もう遅いヨ。



