相手になる話 ―アルマイトの栞 vol.125
 英語であれ、日本語であれ、言語を外国語として習得するならば、「会話」は確かに有効な手段である。そのような「会話」の相手役を、月に1、2回で好いからやって欲しいと知人から頼まれた。そのくらいの頻度なら、まあ構わないかと思って引き受けた。引き受けて、気付いた。何を会話すれば好いのだ。「さあ会話しましょう」などと始まる会話を経験したことがない。そもそも他人同士の会話において、話が初めから終わりまで噛み合い続けることなど、ない。もしそんな状況があるとすれば、それは虚構の世界だ。いっそのこと、吉田戦車さんの『伝染るんです。』を台本にして会話するのはどうか。登場人物たちの会話は常にすれ違うが、じつのところ、日常会話とはそんなものだ。
英語であれ、日本語であれ、言語を外国語として習得するならば、「会話」は確かに有効な手段である。そのような「会話」の相手役を、月に1、2回で好いからやって欲しいと知人から頼まれた。そのくらいの頻度なら、まあ構わないかと思って引き受けた。引き受けて、気付いた。何を会話すれば好いのだ。「さあ会話しましょう」などと始まる会話を経験したことがない。そもそも他人同士の会話において、話が初めから終わりまで噛み合い続けることなど、ない。もしそんな状況があるとすれば、それは虚構の世界だ。いっそのこと、吉田戦車さんの『伝染るんです。』を台本にして会話するのはどうか。登場人物たちの会話は常にすれ違うが、じつのところ、日常会話とはそんなものだ。

 かなり以前から気になっていたのは、創元ライブラリの巻末に掲載された『中井英夫全集』の自社広告である。そこには中井英夫の全集を刊行する旨を告知する文章や、作品紹介の文章があり、それじたい出版社の自社広告としては当然のことだ。どうにも気になったのは、その文章である。「彫心鏤骨の文体によって」。だしぬけに、難読だ。繰り返すが、これは出版社の広告文であって、中井英夫の書いた文章ではない。出版社の誰かが書いたのだと思うが、これを書いた人は「鏤」の字が好きなのか、全集の第4巻を紹介する文章には次のような記述がある。「鏤めた」。読めない。そもそも、「鏤」の字は何と読むのか。自社広告を装った漢字検定ではないかと思った。
かなり以前から気になっていたのは、創元ライブラリの巻末に掲載された『中井英夫全集』の自社広告である。そこには中井英夫の全集を刊行する旨を告知する文章や、作品紹介の文章があり、それじたい出版社の自社広告としては当然のことだ。どうにも気になったのは、その文章である。「彫心鏤骨の文体によって」。だしぬけに、難読だ。繰り返すが、これは出版社の広告文であって、中井英夫の書いた文章ではない。出版社の誰かが書いたのだと思うが、これを書いた人は「鏤」の字が好きなのか、全集の第4巻を紹介する文章には次のような記述がある。「鏤めた」。読めない。そもそも、「鏤」の字は何と読むのか。自社広告を装った漢字検定ではないかと思った。 昨年の11月、京王線に乗っていたときのことだ。通り過ぎる駅のホームの光景と一緒に、つげ義春さんの巨大な絵が視野を横切った。一瞬の出来事に、「なんだ、今のは」と思わず口走ったら、友人も「つげ義春、『ねじ式』が、絵だった」と、意味の解らないコトバを発した。『ねじ式』の冒頭の絵が、B0版らしき大きさで貼ってあったのだ。気にならないわけがなく、あとで調べたら、それは府中市美術館で開催された『石子順造的世界』のポスターだと判明し、『ねじ式』の原画も展示されているとの触れ込みだった。会場で販売された図録の表紙は、京王線から垣間見たポスターと同じデザインで、その図録は美術出版社から一般書店にも並んだ。売れるに決まっている。
昨年の11月、京王線に乗っていたときのことだ。通り過ぎる駅のホームの光景と一緒に、つげ義春さんの巨大な絵が視野を横切った。一瞬の出来事に、「なんだ、今のは」と思わず口走ったら、友人も「つげ義春、『ねじ式』が、絵だった」と、意味の解らないコトバを発した。『ねじ式』の冒頭の絵が、B0版らしき大きさで貼ってあったのだ。気にならないわけがなく、あとで調べたら、それは府中市美術館で開催された『石子順造的世界』のポスターだと判明し、『ねじ式』の原画も展示されているとの触れ込みだった。会場で販売された図録の表紙は、京王線から垣間見たポスターと同じデザインで、その図録は美術出版社から一般書店にも並んだ。売れるに決まっている。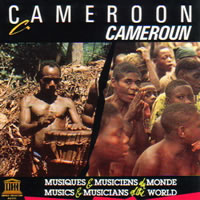 編集中の映像に、やはり曲を付けたいシーンが出て来てしまうわけで、自分でチマチマと音を並べ始めてしまった。気の向くまま音を並べているうちに、ふと思った。「この曲はどのようにして終わるのか」。自分で作り始めておきながら、無責任な疑問である。とりたてて何の計画も描かずに、ボンヤリと音を鳴らし始めた自分が悪い。まるで「即興歌」だ。「唄って」はいないけれど。となると、「即興演奏」とか「インプロヴィゼーション」などとカッコイイ呼び方をしたくなるが、やはり実態は「即興歌」であるらしく、『カメルーン・ピグミーの音楽』の収録曲を思い出した。どの曲も、なんとなく始まり、なんとなく終わる。「子守歌」は、子どもが寝付いたらエンディングなのだ。
編集中の映像に、やはり曲を付けたいシーンが出て来てしまうわけで、自分でチマチマと音を並べ始めてしまった。気の向くまま音を並べているうちに、ふと思った。「この曲はどのようにして終わるのか」。自分で作り始めておきながら、無責任な疑問である。とりたてて何の計画も描かずに、ボンヤリと音を鳴らし始めた自分が悪い。まるで「即興歌」だ。「唄って」はいないけれど。となると、「即興演奏」とか「インプロヴィゼーション」などとカッコイイ呼び方をしたくなるが、やはり実態は「即興歌」であるらしく、『カメルーン・ピグミーの音楽』の収録曲を思い出した。どの曲も、なんとなく始まり、なんとなく終わる。「子守歌」は、子どもが寝付いたらエンディングなのだ。 鈴木一琥さんのダンス公演『3.10』はどうにか終演。御来場頂いた皆さま、ありがとうございました。それにしても、照明の色が気付けば赤系統ばかりになっていた。「意識的に無意識」な照明プランを作ったら、そのようなことになった。どうも、放っておくと自分は赤系の色を選ぶ傾向にあるらしいのだが、『3.10』公演の一週間ほど前に映像作家のOさんと一緒に作業した映像編集が影響したような気もする。半村良さんの作品にちなむ場所を歩いて撮影した映像をコラージュ風に編集することを試みる中で、赤系統の色だけを残すシーンを混ぜてみたりする実験を延々と繰り返していたのだ。気付かぬうちに映り込んでいた派手なピンク色の家がいきなり目立ったりする。どんな趣味の家なのか。
鈴木一琥さんのダンス公演『3.10』はどうにか終演。御来場頂いた皆さま、ありがとうございました。それにしても、照明の色が気付けば赤系統ばかりになっていた。「意識的に無意識」な照明プランを作ったら、そのようなことになった。どうも、放っておくと自分は赤系の色を選ぶ傾向にあるらしいのだが、『3.10』公演の一週間ほど前に映像作家のOさんと一緒に作業した映像編集が影響したような気もする。半村良さんの作品にちなむ場所を歩いて撮影した映像をコラージュ風に編集することを試みる中で、赤系統の色だけを残すシーンを混ぜてみたりする実験を延々と繰り返していたのだ。気付かぬうちに映り込んでいた派手なピンク色の家がいきなり目立ったりする。どんな趣味の家なのか。
